FPSゲームをプレイする上で「意思疎通」が勝敗を分ける…なんて、もう耳タコかもしれません。でも実際のところ、あの一瞬の判断ミスや連携ミスって、単純に「伝わってなかった」ってケースがめちゃくちゃ多いんです。
特に、ValorantやApex Legendsのような高テンポの試合では、ボイスチャットが騒がしすぎて「誰が何言ってるか分からない」状態がよく起こる。そんなとき、無音でも意味が通じる“Ping”の存在がめちゃくちゃ助かる。
この記事では、FPSにおける三大戦術ワードとも言える「Ping(ピン)」「Flank(フランク)」「Hold Angle(ホールドアングル)」の基本と活用術を、連携プレイを重視したい人向けに分かりやすく紹介していきます。
実はこれ、ただの単語解説じゃありません。僕自身も元々「報連相」とか苦手で、口下手なタイプ。でもこの3つの技術を理解してから、ソロプレイでも戦術連携が取れるようになって、TOXICなVCに頼らずにチームで勝てる確率がグッと上がったんです。
次はそれぞれの技術について、実際のプレイシーンを想定しながら、具体的に掘り下げていきましょう。
Ping(ピン)とは? 基本と効果的な使い方

ゲーム内のping(位置や指示通知ツール)は、雑音の多いボイスチャット中でも味方に正確に情報を伝える重要手段です。特に「Ping vs Callout」問題でも、声が通じにくい場面で代替手段として機能します。FPSにおいては「いかに瞬時に状況を共有できるか」が戦況を左右するため、Pingはもはや必須のコミュニケーションツールと言えます。
Ping は音声過多時でも有効?
音声チャットが騒がしいと、有効なコールアウト(声による報告)が埋もれてしまいます。そんな時でも、Pingなら画面上に「敵がここにいる」「ここを攻める」「警戒して!」といった情報を直感的に伝えられます。
例えばValorantでは、敵の位置Pingだけでなく、武器の場所やスパイク設置ポイントなどもPingできる仕様になっており、音が聞こえない状況でも味方と正確に連携が取れるのが強みです。騒がしい深夜のボイスチャット、外国人と当たるマッチング、聞き専プレイヤー…そんな時にもPingは最強です。
敵・位置・指示系Pingの違い
Pingには複数のタイプがあり、それぞれ使い分けが重要です。
- 「敵」Ping:敵の居場所を即座に共有。撃たれた方向や視認した位置をピンすることで、味方が即座にカバーに回れます。
- 「位置」Ping:マップ上の重要ポイントや装備の位置を共有。「ここに武器がある」「ここを通ろう」などの提案に使えます。
- 「指示」Ping:「このポジションを守れ」「この方向を見て」などの戦術的な指示に活用。特にソロランクでは貴重な戦術共有手段。
VCが使えない、あるいは使いたくないプレイヤーにとって、これらのPingは文字通り命綱です。
Flank(フランク)とは? 側面からの動き方

Flankは敵の死角や側面、あるいは背後から攻撃するムーブのことです。戦術FPSでは「正面突破」は危険を伴う場面が多く、Flankによる奇襲は重要な勝利手段となります。
サイドからの奇襲で有利になる理由
正面に構えている敵は、その方向に意識が集中しており、サイドや裏からの攻撃には無防備になります。Flankを成功させることで、1キルどころかラウンド全体を崩す起点にもなるのです。
例えば、Dust2のBサイト裏からのFlank成功例では、1人の裏取りでA側全体の防衛が崩れ、結果として大逆転に繋がったというケースもあります。プロシーンでもFlankerの判断力とタイミングは評価されやすく、特にIGL(インゲームリーダー)との連携が肝です。
チームと連携する Flank の報告タイミング
Flankの成功率を高めるには、「黙って裏取りする」だけではなく、適切なタイミングでの報告が不可欠です。
- Flank前:「これから右から回る」「今から裏取るよ」など短く伝える
- Flank中:「あと5秒で入る」「前面のヘイト集めて」などタイミングの調整を共有
- Flank後:「1キル取った」「バレた!カバー欲しい」など結果を簡潔に報告
この流れを徹底することで、味方のフォローが入りやすくなり、Flank成功率が飛躍的に上がります。
Hold Angle(ホールドアングル)を理解しよう

Hold Angleは、敵が通過するであろう角度を定点で見続けて待ち構えるテクニックです。防衛時や待ち伏せにおいて極めて有効で、特にスナイパーやAR使いにとっては必須スキルとも言えます。
角を“固定して守る”とはどういうこと?
「固定」とは、AIMを常に同じ角度に置いておき、敵がそこに現れた瞬間に撃てる状態を維持すること。これにより、不必要な視点移動が減り、反応速度が速くなる。
例えば、狭い通路の出口をHoldする場合、敵はそこからしか出てこないため、先に見ている側が圧倒的有利になります。これは「アングルアドバンテージ」とも呼ばれ、視点先行で構えている方が勝ちやすい理由の1つです。
Hold Angleを使うべき状況とコツ
- 長い通路や一方通行ルートなど、敵の進行先が限定されている場所
- スナイパーライフルやDMRを使用する場合の高リターンポジション
- 「敵が来そうだな」と予想できるが動きたくないタイミング
Hold中は反応速度が命。逆に言えば、瞬間的なエイム勝負に自信がない時には不向きとも言えます。また、3秒ごとに視点をわずかにズラしてスキャンする「アンチプリファイア」対策も重要です。
Ping / Flank / Hold Angle の組み合わせ活用

これら3つの概念を単体で使うだけでなく、組み合わせることで戦術の幅が格段に広がります。特に「ソロで味方に合わせるのが苦手」「意思疎通が難しい」と感じている人には、非言語的戦術連携の入門として最適です。
例:Ping+Holdでの場持ち戦術
「敵ここに来るかも」とPing → 味方がその位置をHold Angleでカバー。すると、敵はそのPingされた位置に警戒心が向かい、移動が制限されます。
このように、Pingが“敵を誘導する罠”として機能することもあり、守備側で場を持たせたい時には特に有効です。VCが無いパブリックマッチでも成立するのが魅力。
例:Flank+Pingで奇襲成功率アップ
Flank前に、敵の視線を誘導するようにPingを打つ。すると味方が正面からプレッシャーをかけ、敵がそちらに集中。
その隙に裏からFlankすることで、敵に気づかれる前にキルが取れます。この連携は、Pingを「情報共有」ではなく「情報操作」に昇華させた好例です。


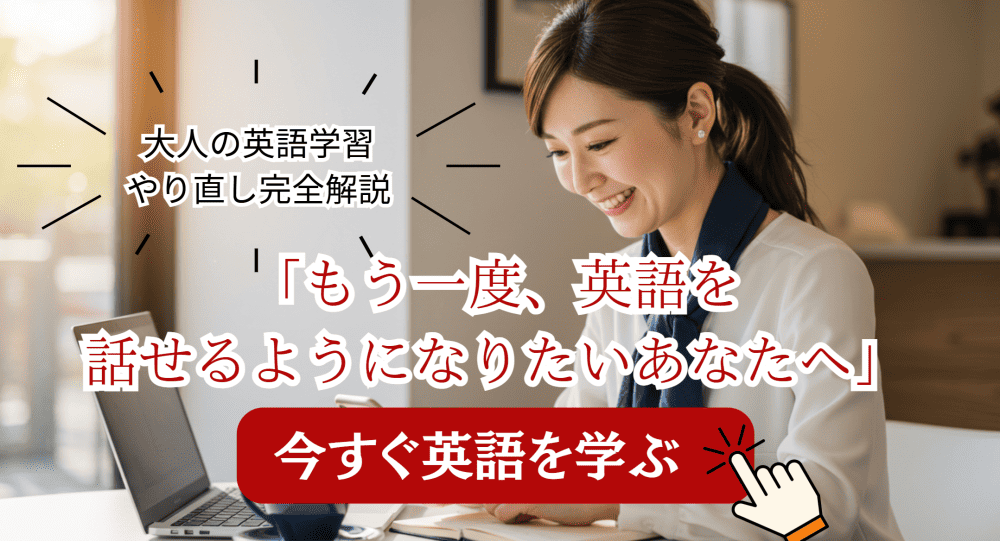
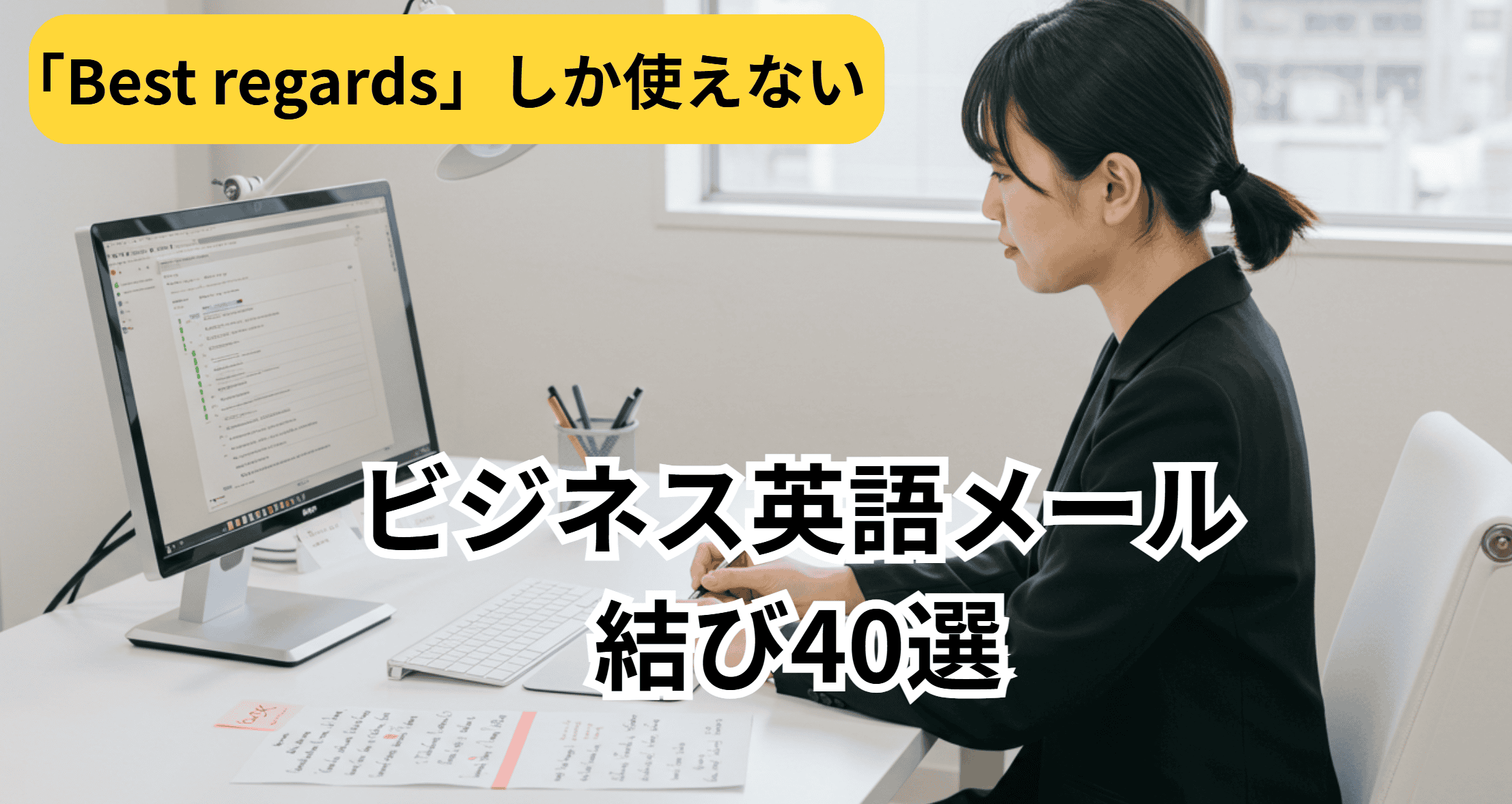









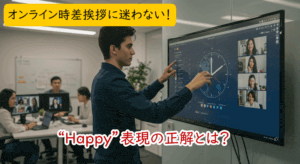


コメント