「聞き取れないところが分かると、リスニングは面白くなる。」
TOEICのリスニング対策に悩んでいるあなたにこそ、試してほしいのが「2色ディクテーション」です。私も中卒で英語が大の苦手だった頃、どれだけ聞いても「何言ってるか分からん!」状態が続いていました。でも、ある日2色ペンを手に取って書き分けてみたところ、音の輪郭が見えはじめたんです。
この学習法は、ただの書き取りではありません。「なぜ聞き取れなかったのか?」を色で分析できる、心理学的にも非常に効果のある手法です。
今回は、TOEIC満点を目指す人から初心者まで使える「2色ディクテーション」の具体的なやり方と、私が実践して効果を感じたノウハウをまとめました。目からウロコのリスニング勉強法、一緒に深掘りしてみましょう!
2色ディクテーションとは?やり方と効果
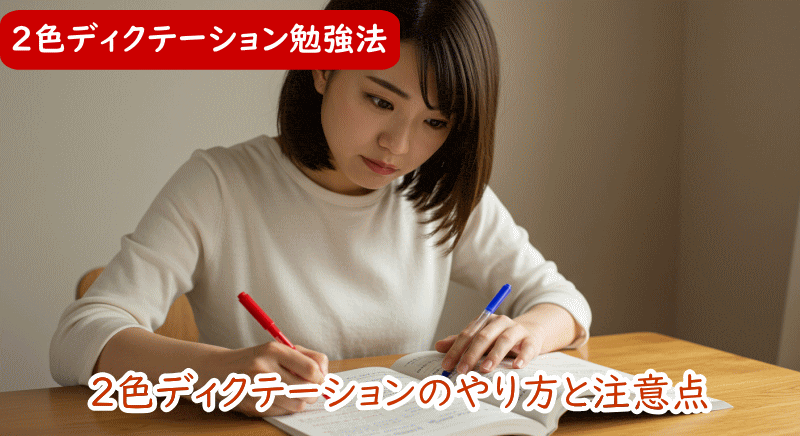
「2色ディクテーション」とは、リスニング音声を書き起こす際に、2色のペンを使って“聞き取れた音”と“聞き取れなかった音”を色分けして記録する学習法です。見た目は単純ですが、これが驚くほど記憶に残るんです。
やり方はとてもシンプル。
- 英語音声を再生しながら、聞こえた通りに書き起こす(1色目:黒など)
- 曖昧に聞こえた部分、自信がない単語は2色目(赤など)で記録
- スクリプトで正解を確認し、どこを間違えたのか・聞き取れなかったのかを分析
- 必要があれば再生しながら書き直す
この「書き分ける」という行為が、記憶の定着や弱点分析に繋がります。心理学的にも、視覚と聴覚を同時に使う学習は脳の働きを強化しやすいとされており、TOEICのリスニング対策として非常に効果的です。
2色ペンで書き分けるメリットは?
2色ディクテーションの最大の強みは、「自分が何を聞き逃しているのか」が目に見える形で分かることです。
例えば、
- 黒:聞き取れた音
- 赤:聞き取れなかった/不確かな音
こうして記録すると、リスニングの弱点が一目瞭然。特定の単語の語尾がいつも赤くなる場合、それは音声変化に弱い証拠です。また、後で見返す際にも「赤部分=要復習ポイント」と明確なので、復習の効率が劇的に上がります。
さらに、目で色を追うことで記憶の強化が期待できる点も大きなメリットです。
3色ペンとの違いや選び方
2色ディクテーションに慣れてくると、「3色使ったらどうだろう?」という発想が出てきます。確かに、3色にすれば「聞き取れた/あいまい/聞き取れなかった」の三段階で分類できるメリットもあります。
しかし、個人的には初心者〜中級者の段階では2色で十分。理由は以下の通りです。
- 分類がシンプルで迷いがない
- 記録スピードが速い
- 精神的な負担が少ない
色が増えると、その分判断も増えます。「この音は赤か?オレンジか?」と迷う時間がもったいない。最初は2色で始めて、精度が上がったら色数を増やすのがオススメです。
TOEICリスニング満点者が実践する実際の進め方

リスニング満点を取るような学習者は、2色ディクテーションを「ただの書き取り」とは考えていません。使い方は非常に戦略的です。
ステップは以下の3つ
- 分析:まず聞こえたまま書き起こし、赤と黒で色分け
- 再生:聞き直して正答と比較し、何が聞き取れなかったか把握
- 反復:同じ素材を再利用して再ディクテーション、またはシャドーイングへ移行
この3ステップを繰り返すことで、「正確に聞く→意味を取る→音を再現する」というプロセスが身に付き、満点が狙える耳になります。
Part2・短文に特化したディクテーション手順
TOEIC Part2(応答問題)は、短くてシンプルな英文が多いため、2色ディクテーションの練習素材として最適です。
おすすめの手順
- 音声を再生(最初は1文あたり3回までOK)
- 黒で聞こえた通りに書く
- 赤で自信がなかった部分を補完
- スクリプトで答え合わせ
- もう一度再生して再確認
省略音(wanna, gonna, lemme)や連結音が頻繁に出てくるので、赤でそれらを明示的に記録することで、耳の感度が高まります。
音声変化・発音に気づく分析のコツ
ディクテーションの醍醐味は、書き取りを通して「音声変化に気づける」ことにあります。
例
- “did you” → “didja”
- “going to” → “gonna”
- “want to” → “wanna”
こうした変化は、学校英語ではほとんど習いません。ですが、実際のネイティブ会話では必ずと言っていいほど出てきます。
2色ディクテーションでは、こうした音声変化を赤で記録し、再確認することで「聞こえる耳」を育てることが可能になります。
継続するための時間配分とノート術

継続こそ英語学習の命。2色ディクテーションも「無理なく続ける仕組み」を作れば、確実に成果が出ます。
ポイントは2つ
- 毎回の学習時間は10〜15分に区切る
- ノートを左右見開きで使う(左:自分の書き取り、右:スクリプトと答え合わせ)
このスタイルなら、日々の学習負担が軽く、記録も整理しやすくなります。忙しい社会人にもおすすめです。
初心者でもできる!2色ディクテーション継続法
「英語が苦手」「続かない」という方でも大丈夫。最初は週3回、1日10分からでOKです。
- 月・水・金でディクテーションの日
- 使う教材は1文ずつ音声を再生できるもの
- ノートはシンプルに左書き取り、右答え合わせ
このルールだけで、3週間後には確実に「聞き取れる感覚」が芽生えてきます。小さな成功体験を積み重ねることで、学習のモチベーションも自然と高まります。
効果を最大化!おすすめ教材と活用法
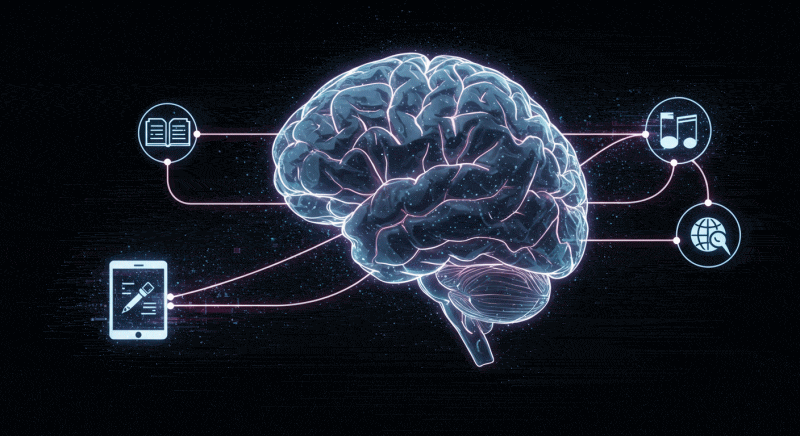
2色ディクテーションの効果を最大化するには、「教材選び」も非常に重要です。
以下の条件を満たす教材を選ぶと良いでしょう。
- 音質がクリア
- 音声スピードがTOEICレベル(速すぎない)
- スクリプト付き
おすすめ教材
- 『公式TOEIC Listening & Reading 問題集』
- 『スタディサプリ ENGLISH』
- 『究極の英語リスニング』
初心者はPart2中心の教材から、中級者はPart3やPart4の長文へとステップアップしましょう。
ディクテーションを伸び悩みから成績アップへ
「やってるのに伸びない…」と悩む方は、ディクテーションの“記録”と“反復”が足りない可能性があります。
実際に、スタディサプリENGLISHの音声を使って2色ディクテーションを3週間継続したある社会人は、TOEICリスニングスコアを75点アップさせました。鍵は「赤で聞こえなかった箇所を可視化→徹底復習」というプロセスにあります。
シャドーイングとの比較:どっちが先?
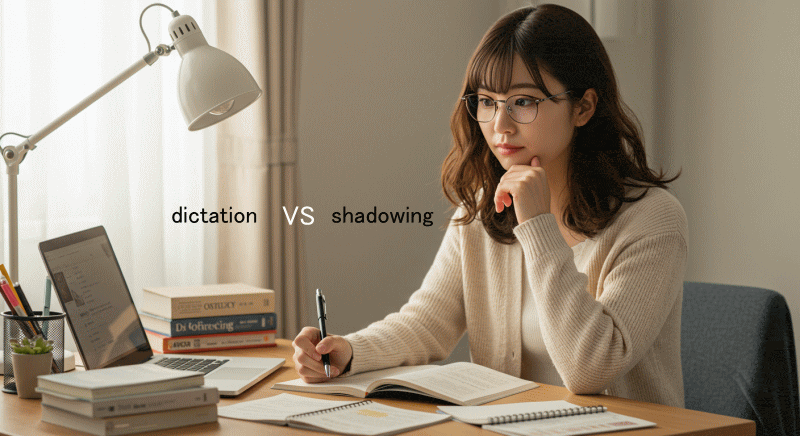
最後に、よくある疑問「2色ディクテーションとシャドーイング、どっちが先?」について。
答えはシンプル。
まずは2色ディクテーション→その後にシャドーイング。
理由
- ディクテーション:正確に聞き取る訓練(インプット精度)
- シャドーイング:聞きながら即発音する訓練(反応速度)
土台となる“聞き取れる耳”を作らずに、シャドーイングだけしても効果は薄いです。逆に、ディクテーションで音を正確に捉える力をつければ、その後のシャドーイングが格段に楽になります。



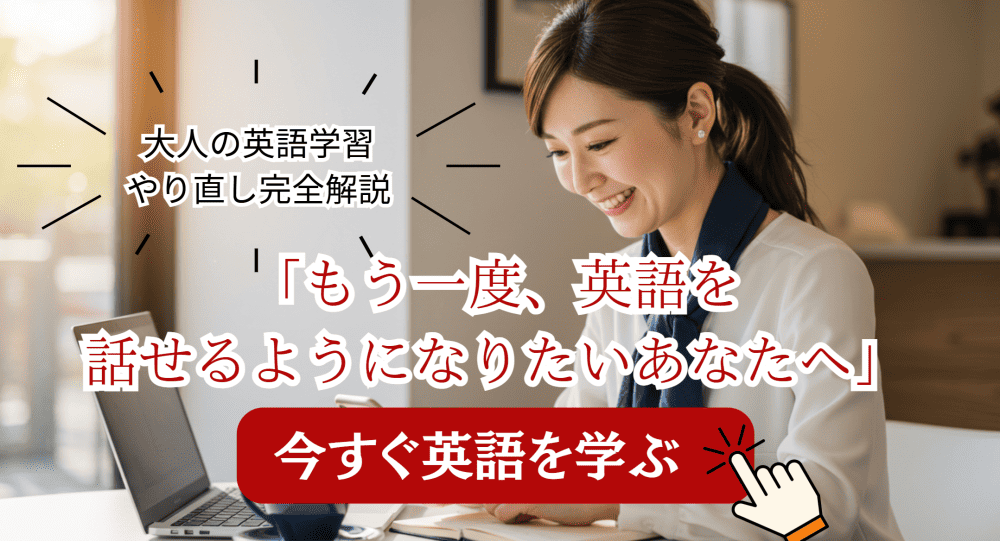
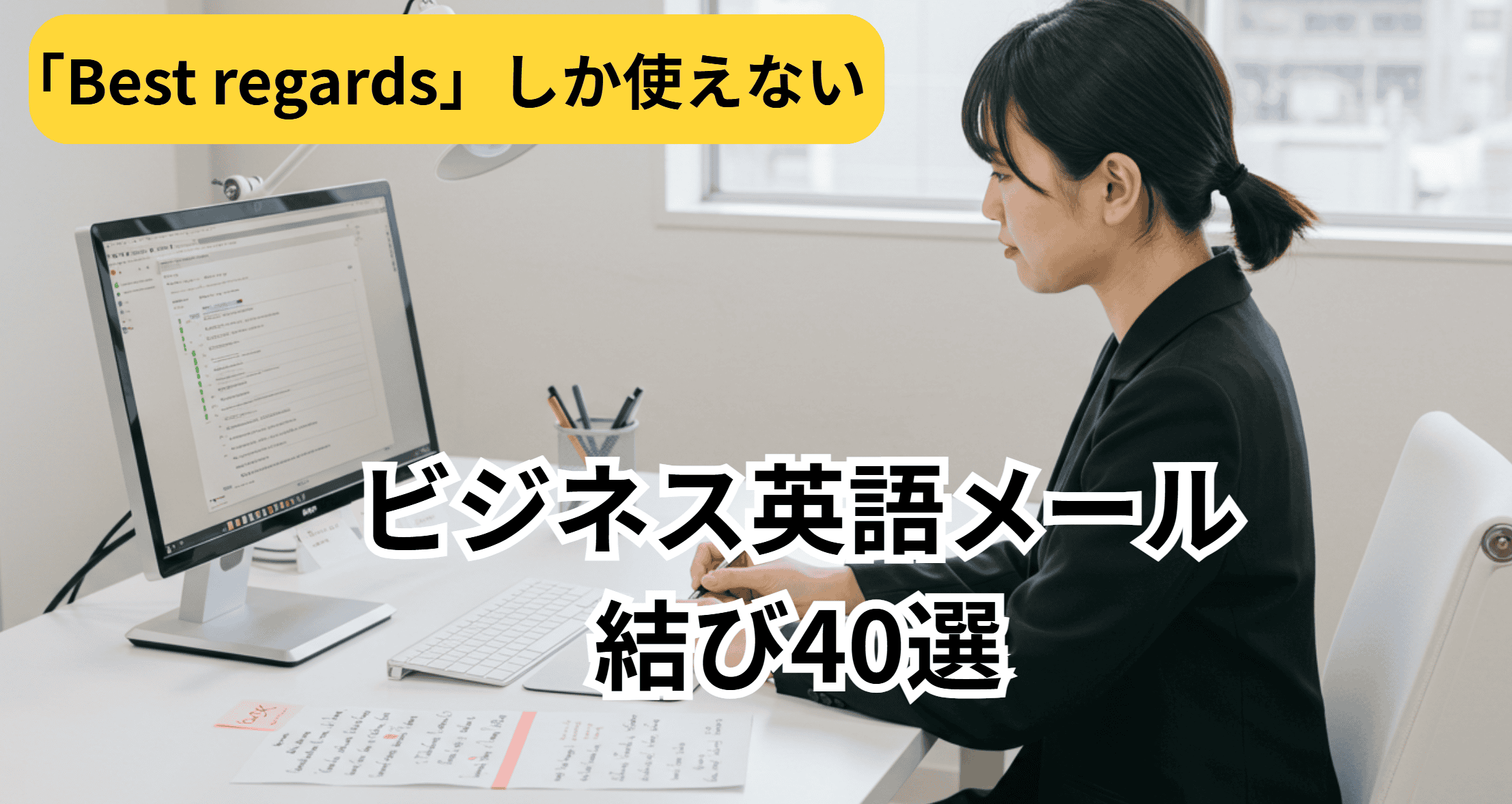




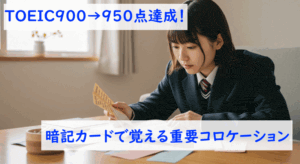
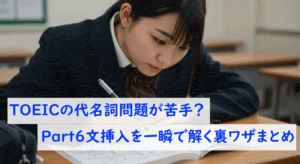
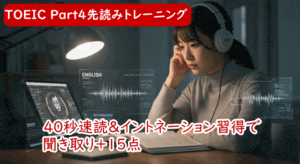
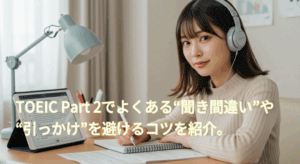
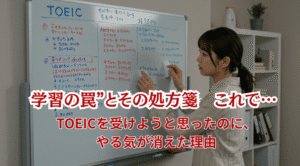
コメント